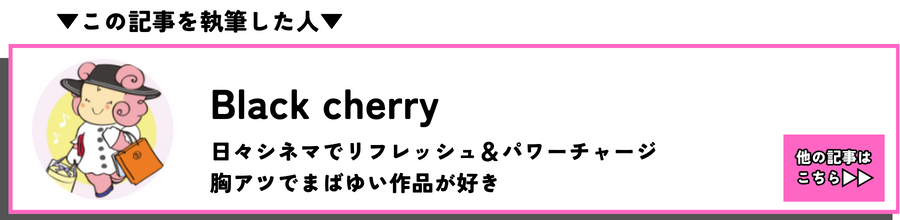フェデリコ・フェリーニ「道」
今回ご紹介するのはイタリアの巨匠フェデリコ・フェリーニの「道」(1954年)です。
とにかく尊い✨珠玉の名作です。
はじめてみたのは○十年前の学生時代。それがヒューマニズムなのか何かわからずとも、胸を打たれました。
《監督フェデリコ・フェリーニについて》
1920年生まれ、イタリア北部出身。新聞マンガ家・コラム記者、ラジオドラマの放送作家などを経て映画界へ。本作「道」は、ヴェネチア国際映画祭・銀獅子賞、米アカデミー賞外国語映画賞などを受賞。「カビリアの夜」(1957年)、「8 1/2」(1963年)などで国際的に評価され、その後20世紀を代表する映画監督のひとりというほどの巨匠へと歩まれたお方です。


《おもな登場人物》
●ジェルソミーナ(ジュリエッタ・マシーナ)
純粋な心を持つ風変わりな女の子。大道芸人ザンパノに嫁いで亡くなった姉に代わり、彼の後妻になる。ザンパノのスパルタ指導のもと、大道芸を手伝うようになる。おそらく知的障害がある。
●ザンパノ(アンソニー・クイン)
粗野な大道芸人。傲慢で乱暴者。鎖を胸に巻き付けてちぎる芸が十八番。
●イル・マット(リチャード・ベイスハート)
優しい綱渡り芸人。旧知の仲であるザンパノをたびたび揶揄し、冗談のつもりが敵視される。
《ストーリー》
※ネタバレしないように途中までです
大道芸人ザンパノは、妻ローザの実家にオート三輪を乗り付け、彼女が死んだことを告げる。貧しい一家は哀しみつつ、ローザの妹・ジェルソミーナをザンパノの後妻として送り出すのだった。たった1万リラで売られる形で、ジェルソミーナは粗野なザンパノに連れられ巡業の旅へ。
暴力をふるい、方々で行きずりの女と楽しむザンパノとの旅路は、ジェルソミーナにとってつらいものだった。
ある日出会った陽気な綱渡り芸人イル・マットは、ジェルソミーナが唯一心を砕く相手となる。「私はなんの役にもたたない女」、「この世で何をしたらいいの」と泣くジェルソミーナに「この世にあるものは、たとえ石ころでもなにかの役に立ってる」と語るイルマット。
彼はザンパノをからかい、ジェルソミーナにラッパを教えるなどしたことで、ザンパノの怒りをかう。この怒りが、事件を引き起こしてしまう・・💦
《ジュリエッタ・マシーナ/唯一無二の存在感✨》
フェリーニは「8 1/2」「甘い生活」のような不思議感のある作品で有名な気がしますが、「道」はリアリズム作品。大道芸やサーカスが登場するものの、ファンタジックな展開はありません。
舞台は、第二次世界大戦後10年とたたない頃のイタリアの寒村や市街地など。旅芸人のザンパノ・ジェルソミーナは国内各地を転々とし、ローマ近郊なども登場しますがほとんどの景色は荒涼としたものです。
そんななか、ジュリエッタ・マシーナのピュアな存在感が際立ちます。後にも先にも「こういうキャラはみたことない・・!」というのがマシーナのジェルソミーナなんです(ジュリエッタ・マシーナは、フェリーニが長年連れ添った奥さんでもあります。おしどり夫婦で知られ、1993年にフェリーニ、その翌年後を追うようにマシーナが亡くなったニュースは、当時衝撃でした)。
《愛は人を変えることができるのか》
存在感が圧倒的でありながら、ジェルソミーナは終盤手前で姿を消してしまいます。本作のラストを飾るのはザンパノ。終始憮然として凶暴で、それまであたたかみの微塵も宿さなかった男が泣くとき、まさにこういう風に泣くものでは・・と心底思わせてくれるアンソニー・クインはさすが名優です。このラストも、つくづく必見です。
本作を思うとき、「愛は人を変えることができるのか」という問いが浮かびます。
この普遍的な問いかけを、本作は全編登場するザンパノという冷徹な人物を通して投げかけている、そんなふうに感じるのです。
《ニーノ・ロータによる忘れがたい旋律》
テーマ曲を手がけたのは、他フェリーニ作品や、「太陽がいっぱい」のテーマ、「ゴッドファーザー愛のテーマ」などで知られるニーノ・ロータ。イル・マットがバイオリンで奏でる素朴な旋律は、ジェルソミーナのラッパへ、やがてはある海辺の地に住む少女の歌へと受け継がれていきます。ザンパノがその海辺に巡業で訪れ、ジェルソミーナの辿った運命を知る手がかりとなるのがこのテーマ曲。優しさと哀しみが表裏一体となって迫るこの音楽は、本作に欠くことのできない彩りとなっています。